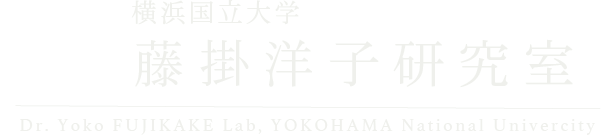私の所属は、横浜国立大学大学院都市イノベーション研究院になります。
都市イノベーション研究院では、私のような文化人類学(あるいは「開発の人類学」、もっというならば開発人類学)や社会学などの社会科学系を生業とする教員もいれば、都市交通や建築を専門とする教員もいます。いわゆる文理融合の大学院になるわけです。
私はこの文理融合という概念は十分に受け入れておりますし、必要であると思っています。開発途上国や新興国で社会開発に関わるにも、村の女性たちの支援のために一村一品運動を繰り広げるにも、インフラが整備されなければ社会開発が先に進まない場面に多々遭遇してきたからです。また、教育の質の向上が重要とわかっていても、学校がなければ勉強ができない、教室がなければ雨の日や灼熱の太陽が照りつける日はとてもではないけれども学校に行くことができない時もあれば、学校に到着しても勉強ができないということがあります。村の住民からの要請も受け、パラグアイ農村部に学校を作るお手伝いをさせて頂き、4つの小学校他を建設させていただきました。
インフラ整備の重要性や文理融合の重要性は十分に理解しているつもりであります。一方、今回のパラグアイ渡航で村で学生たちや(特活)ミタイ・ミタクニャイ子ども基金関係者のメンバーも含め、パラグアイのとある村において道普請のお手伝いをさせて頂いたのですが、立ち止まって考える必要がある思う部分がでてきて、・・・そう改めて文化人類学者的発想がむくむくと湧き上がってきたのでした。
そのこととについて今から少し書いてみたいと思います。
とある村では、数年前からコンフリクトが起きていました。もちろん、初めて村に入った人にはわからないようなものです。数年間の関わりの中で、その村で起きているコンフリクトを解消するために道普請をしてみてはどうかという話になりました。今年の5月頃から村の関係者と打ち合わせをはじめました。11月上旬には私自身が村に入り、道委員会の関係者にも個別にも意見をうかがい、村の教会においても参加している村人全員に説明をさせて頂き承認を得ました。その後も、村にある組合メンバーや保護者会、その他の委員会のメンバー、村の女性も子どもたちの参加した住民集会において道普請をすることを村の会議で決定しました。
その後、日程がしばらく空き、雨が降った翌日、道普請の日がきました。
農民の方々は作物を収穫しないといけないということから、予定していた数の村人は参加できず、一部の村の方々と日本側の関係者による道普請の実施となりました(道普請の当日、私はその場にはいませんでした*)。
*私は仕事の都合で日本に先に帰国する必要があり、道普請は他の専門家の先生にお任せをしました。道普請の結果、村の道が平坦になり関わった村の方々も日本側からの参加者も大変満足されていたということです。形になってみえる国際協力の強みはここにあると思います(私も生活改善普及員として料理指導などをさせて頂いてきたのですが、料理が形になり、おなかも満足する、とても良い仕事だと思っていました)。
一方、村人が来なかった/来れなかったことによりおきるインパクト(ポジティブな面もありますが、ここでは主にネガティブな面)をきちんと評価する必要があると考えています。その評価のあり方は色々ありますが、道普請の実施が外部者の自己満足であったり、一部の村人にのみ裨益する状況でははいけないと考えます。もちろん、村全員の合意が取れていれば良いのですが、今回はどうだったのか改めてヒアリングが必要だと考えます。
悪い道が補修されれば、村の人々の利便性は格段に向上されます。その点は間違いないと考えます。今回は、関係者が、この場所の普請は行うということを村人と話し合い、集会でお伝えし、村でも合意形成をしておりました。日本側の若手の参加者の学習のためにも、というエクスキューズがあったわけですが、コミュニティのエンパワーメントという意味においてはいくつかの課題がまだ残っていると考えます。
支援活動には時間が限られるものが多いため、悠長なことを言えない場面も多いですが、やはり立ち止まって考えたい。対象地域の方々あっての支援だと思いますし、ここで立ち止まって考えることをやめることだけは、やめたくない、そんなことを思った瞬間でした。村人が数名しか集まらない中で、合意が取れているとはいえ、本当に道普請を行って良かったのかという点についてはもう少し考えてみたいと思います。
幸いにも日本の関係者が一名現地に残りましたので、この点はきちんと話し合い、村の方々にとっても今後も気持ちよく道普請ができるような仕組みと道普請で出ていく費用(機械が壊れてしまい、その補修費用も参加した人も持ち出しになるなどがないような)のルール作りと役割分担ができるような仕組みを作る必要があると考えます。
話は少しそれますが、私が学生時代に文化人類学の先輩諸氏、指導教官から口をすっぱくして言われたこと、それは個人の家に泊まるなということでした。指導教官の話は、日本の村を事例にした話でしたが、途上国や新興国の村でも同じことが言えると考えます。関わりが多い人との情報量は蓄積されます。この点を「平等」や「民主主義」という観点から日本人はどう考え、アメリカ人はどう考えるのか、いくつもの事例に遭遇してきましたので、近い将来、この点についても考えてみたいと思います。
道を一つとっても、学校建設を一つとっても色々なことを考える機会を頂いております。
感謝して、考えることをやめないように研究と実践を続けたいと思います。
2015/11/26 藤掛洋子(2023/01/14誤字修正)